
自然農法なつながりの知り合いから1冊の本をたまたまお借りしまして。今回渡されたその1冊は、数年前に農業を勉強していた頃なら飛びついているかもしれない冊子のタイトルでしたが、今はそれほどでもなく。
ですが、手元に来たということは、読みなさいというお告げなのかもとも(笑)正直読書嫌いな私ですので、開いた活字に少しくらっとしながら、目に入るところから秋の読書を。
→ 一粒古代小麦アイコーンのひじきスパゲティーレシピはこちら
野菜やお肉や魚などの食材を選ぶときに、マクロな目を持つことの素晴らしさに気付かされることでしょう。
食材やメニューの組み立て方に限らず、体の体調をチェックするための医者の目(望診)のような、人間の営みにも通ずるものが、そこにあると気づかされます。
そもそも、マクロビオティックとは、
マクロ(大きな、全体的な)、ビオ(生命)、ティック(学術)の造語ですので、肉を食べちゃダメ、乳製品を食べちゃダメといった食養に関するものではないのですが。

誰かに何かを教える、伝えるとなると、一般的に腹落ちしやすい情報と整備され伝えられるので、それだけが空回りし、いつの間にかそれが正統派の考え方のように伝わる事もありまして。
本来は「世界平和」の願いを前提に、宇宙の秩序にのっとって、自身の体を中庸に保つことが大切であるという教えでもあります。よって、何を食べてはいけないというものではないということに。
冊子によりますと、まず、「野菜」は遺伝と環境により味が決まり、その土地の微生物により育つと語っています。
マクロな視点から田畑の背景に山や川、果ては風を見ることでそこに育つ野菜の良し悪しを予想できるといったことが書いてあります。これはシェフである著者の奥田さん自身が、農家の目線で田畑を見ることができているということでもあります。
次に、魚は捕らえた場所と、その魚が食べた餌で、調理する時の相性の良い組み合わせが決まるとも書いてあります。
例えばマグロで言うと、太平洋を北上するマグロの場合、最初に鰯を主に食べているマグロは、鰯によく合うフェンネルという香菜がとてもよく合うマグロなのだとか。そして、三陸あたりで秋刀魚を主に食べているマグロは、秋刀魚の脂肪がマグロ自体にも含まれるため、オイルを控えめに調理しても美味しくいただけるようになっているのだとか。面白いことに、日本海を北上するマグロは最初、イワシやアジを主に食べていたものが、北上するにつれてイカを食べるそうなのですが、そのころのマグロは、イカに良く合うズッキーニやルッコラという野菜がとてもよく合うのだとか。
ちなみに、魚の色や形で、その魚が住んでいた場所や生き様がある程度見えてくるとも。これは人間の望診に似た見方ではないかと思うのです・・・。
→ グルテンフリーな南瓜まんじゅうレシピはこちら(デーツの餡子入り)
最後に、お肉についても、付け合せの野菜や香菜の大切さを語っていました。驚いたのは、ライオンが、捕らえた獲物を「腸」から食べているという部分。ライオンが食す動物は、草食動物が主ですが、草食動物の腸の中に残っている消化中の草とお肉を一緒に食しているそうで。ライオンもお肉の消化にそれらの植物の力が不可欠だということをおのずと知っているのかもしれませんね。これは人間もしかりで、お肉に付け合せとされている野菜も、お肉と共にしっかり摂ることをマクロビオティックでも推奨しています。
例えば牛肉なら、イモやニンニク。豚肉ならキャベツや生姜、鶏肉ならネギなど。
自主的に始めた読書ではありませんでしたが、この本を通して、食材にこだわりすぎてミクロな視点に陥りすぎずに、まずはマクロな視点から食や物事に対して見るということを、忘れずにいたいものだとあらためて。



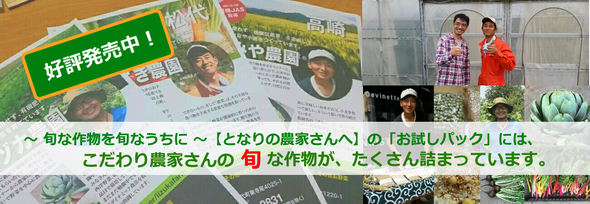
コメントをお書きください